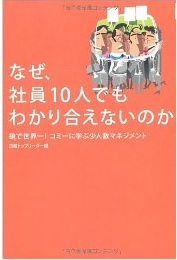「寧静致遠(ねいせいちえん)」。誠実でなおかつこつこつと努力を続けないと、遠くにある目的に到達することはできないという意味。出展は中国の古典『諸葛孔明伝』で、調べてみると、諸葛孔明が自分の子供に書き残した言葉だそうです。故事『三顧の礼』で有名な諸葛孔明の言葉、じっくり味わいたいものです。
さて「寧静致遠」。これは親が子供に言う言葉のなかで、言い方は様々ですが、意味としては一番多いことではないでしょうか。「ちゃんとやりなさい」「まじめにやりなさい」「きちんと続けなさい」等々、私も幼少の頃良く言われたものです。しかし「親の心子知らず」で当時はうるさい小言としか感じませんでした。自分が親になった時にその意味に気づきますよね。
翻って会社ではどうでしょうか?「まじめにコツコツ」とは思いながらも、目的が分からなかったり、将来像が見えないと、ただの小言に聞こえたり、継続するのが大変になってきます。
つまり「寧静致遠」とはゴールがしっかりと明確になっていて、それに向かってまじめに一歩ずつ進むことを言うのですね。そしてそのゴールと言うのは、可能であれば「好きな事」「楽しめる事」が良いのではないでしょうか。
先日、株式会社コミーの小宮山社長の話を聞く機会がありました。良く言われますが「コミーは知らなくても、コミーの製品を見たことが無い人はいない」というあの会社です。ATMやコンビニそして航空機まで安全用、防犯用等のミラーを作っている会社です。
数年前、世界最大800人乗りの旅客機「エアバスA380」が就航した際に報じられましたが、ここにコミーが日本の中小企業では唯一サプライヤーとして選ばれました。エアバスは世界最大の2階建て飛行機ということで、世界の一流メーカーの技術が結集され、日本からも三菱重工・富士重工など大手20社が参画しました。その中で確かに機体の主要部分ではありませんが、客室の手荷物入れの中に設置する忘れ物防止用の鏡という、大切なパーツの一つとして、見事に採用されたのです。世界の航空会社で五つ星評価を受けている7社のうち6社(アシアナ、カタール、マレーシア、シンガポール、キャセイパシフィック、海南)で、コミーの手荷物入れミラーが使用されているそうです。
|
コミーは、小さいながらもユニークな製品で選ばれる会社になったわけですが、そこには凄い研究部門があるわけでもなく、凄い営業部門があるわけでもなく、社員20名足らずのいわゆる中小企業です。しかし、そこに至るには創業社長の小宮山氏が会社員時代から、そして創業後も、商売というのはどんなことかを考えて、試行錯誤しながら会社を成長させてきた歴史があります。 |
↑コミーがなぜ、創造に時間を使っているかがわかる本。お勧めです |
このコミーのノウハウを外部の視点から書かれたのが、上記にある本「なぜ、社員10人でもわかり合えないのか」です。これは、コミュニケーションの本質を書いた本ですが、まずは「常識を疑う」というところから、入っています。少人数だからコミュニケーションが取れているはず、から派生し、売れている商品だからお客様のニーズはある、満足していると思いこんでいることが、企業にとっては一番危険だということが書かれています。
コミーでは製品開発の原点をCSではなく、独自の呼び名US(使用者満足度)でとらえています。買ってくれる人(販売店、購買部門等)ではなく、実際に現場で使う人が本当に満足しているのか?何か改善点はないか?を常に現場に出向いてヒアリングをしているそうです。その地道なマーケティングが現在の同社を作っているのだと改めて思いました。
「寧静致遠」 小宮山社長が到達したゴールは、世間のトレンドや時代の流れで商品を考えるのではなく、お客様の不満解消を尽き詰める事だと、試行錯誤の中から見つけたのだと思います。「ビジネスはすべてサービス業」「商品開発の原点は不満の解消」とよく言われていますが、日々の仕事に忙殺されるとコツコツはしていても、目標を見失ったままの作業になりかねません。会社の事業目標を明確にして、そこにむかって着実に続けていく。それが「寧静致遠」の本質であり、成果を出す王道だと思います。
(弊社発行 月刊まるやまVoice Vol.34 2013年7月号より抜粋)