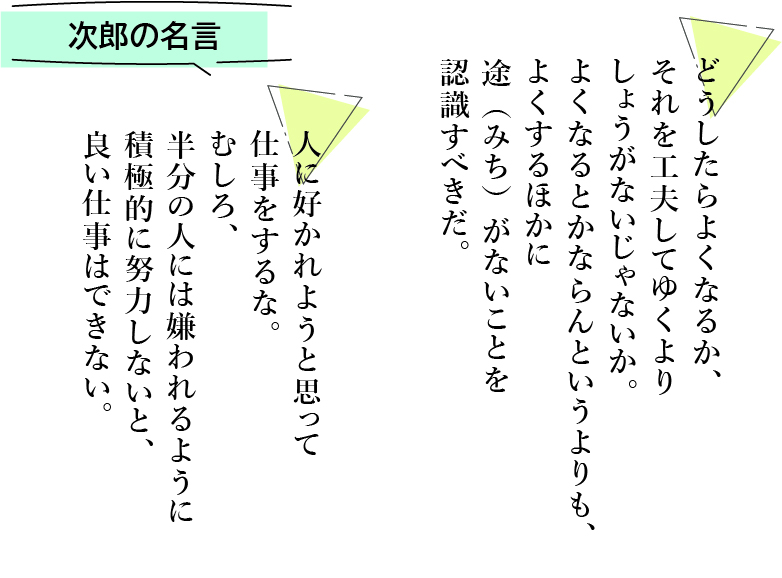世界の混迷と時代が大きく変わろうとしている今、
社長や役員の役割とは-そして日本人として、どのように生きていくべきか。
激動の時代に大局から思考し発信し続けた実業家・白洲次郎の生き様に迫ります。

日本国憲法の成立に大きな貢献を果たしたことで知られる白洲次郎は1902年(明治35年)、兵庫県に生まれました。
祖父は三田藩家老、父はハーバード大学を卒業後、綿の貿易商として大成功を収めた裕福な家庭に生まれ、少年時代は悪ガキとして地元で知られていました。
兵庫県立第一神戸中学校(旧制)卒業後、イギリスのケンブリッジ大学クレア・カレッジに留学、イギリス流のダンディズムやライフスタイルはこの時身につきました。
9年間の滞在後、父親の会社が倒産し帰国することになり、翌年正子と出会い結婚。
その後は英字新聞記者を経て、イギリスの商社であるセール・フレイザー商会に勤務。1937年には日本食糧工業(後の日本水産)の取締役となりました。
商談などで海外に赴くことも多く、駐イギリス特命全権大使であった吉田茂の面識を得、その後の日本の外交において重要な役割を果たすことになります。
「日本人なら日本語を」譲らなかった次郎の正義
1949年に貿易庁長官となり、翌年に通商産業省(のちの経済産業省)を設立。
1951年に行われたサンフランシスコ講和会議では、吉田茂のブレーンとしてGHQとの折衝にあたり、終戦連絡中央事務局で日本国憲法の制定に深く関わりました。
外務省が英語で用意していた吉田茂の演説の草稿を見た次郎は、日本の国威を保つ意味から日本語で演説するよう、吉田に進言。結果、吉田茂は長さ6mにもなる巻物を手に登壇し、「日本全権はこの公平寛大なる平和条約を欣然受諾致します」と日本語で演説を行いました。
敗戦によりアメリカに劣等感を抱き始めていた日本の政治家の中で次郎は、神よりも偉い存在として見られていたGHQを相手に堂々と渡り合い、アメリカに飲まれそうになる日本を再建へと導いたのです。
その毅然とした振る舞いは、GHQに「従順ならざる唯一の日本人」と評価され、吉田茂首相の側近として政治の中枢での活躍ぶりは「白洲三百人力(役人300人分の力がある)」と言われました。
ブレなかった孤高の信念
ケンブリッジ大学で学んだ品格と誇りを生涯大事にしていた次郎は、GHQの民政局長であったホイットニー准将との初対面の席で、「キミは英語がなかなか上手だね」と言われた際にも、「あなたも、もう少し勉強すれば上手になりますよ」と皮肉で返すほどに、誰に対しても怯むことはなかったと言われています。
また、当時外務大臣だった吉田茂とともにサンフランシスコ講和会議に向かう飛行機の中でも、周りの日本人が皆きちんとしたスーツを着用していた中で、白洲次郎はジーンズとTシャツで過ごすなど、戦後の激動の中で、とことんマイウェイを突き進んでいた珍しい日本人でした。
こうした次郎の強気な交渉と明確な戦後復興ビジョンがなければ、日本は敗者としての意識を引きずったままで、歴史的な成長を遂げることはなかったかもしれません。
威厳を持って「主張を貫くスタイル」の背景には、ビジネスの現場でこそ鍛えられる取引や交渉の経験・スキルがあったと言えるでしょう。
≫次週後編へ続く